谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。
- [谷税理士法人]トップページ
- ためばな
- 2024年06月
2024年06月
「2024年06月」の記事を表示しています。
勤続10年を迎えて
- 2024年06月04日
- ためばな
私事ではありますが、今年の1月で勤続10年を迎え、月日の流れの早さを感じると共に、社員皆様の力添えのおかげで、ここまで続けてくることができました。
10年間通い続けた通勤路や事務所周辺ですが、2月末よりお昼休みに始めたウォーキングによって通勤だけでは知りえなかった小畑川から見る山並みや、開放的な景色に感動したり、迷路のような住宅街に「こう繋がっているのか!」と新たな発見があり、10年通い続けていても違う行動を起こすことで、新鮮に感じたり、まだ知らぬ事があるものだなと実感しました。
仕事においても慣れに甘んじず、常に新鮮な気持ちを持ち続け取り組んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。
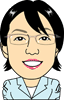
本日の発言者:大野
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
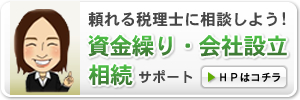
相続でお悩みの方は↓
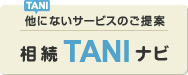
10年間通い続けた通勤路や事務所周辺ですが、2月末よりお昼休みに始めたウォーキングによって通勤だけでは知りえなかった小畑川から見る山並みや、開放的な景色に感動したり、迷路のような住宅街に「こう繋がっているのか!」と新たな発見があり、10年通い続けていても違う行動を起こすことで、新鮮に感じたり、まだ知らぬ事があるものだなと実感しました。
仕事においても慣れに甘んじず、常に新鮮な気持ちを持ち続け取り組んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。
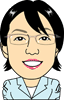
本日の発言者:大野
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
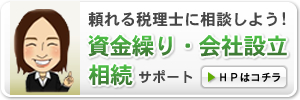
相続でお悩みの方は↓
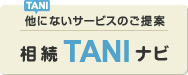
相続時精算課税と住宅資金贈与の持ち戻しについて
- 2024年06月04日
- ためばな
先日知り合いの税理士さんに教えてもらった、精算課税と住宅取得資金の少し細かい注意点についてお話しさせて頂きます。
長くなってしまうので、2つの制度の基礎的な説明は割愛させて頂きます。
この2つの制度を併用して親から子へ住宅取得資金の贈与を行なった時に、精算課税分として、2500万円、住宅取得資金の非課税分として、500万円(一般住宅の場合です)の合計3,000万円について贈与税が非課税で贈与ができます。
そして将来親に相続が発生した場合、精算課税分の2500万円については、相続税の計算の対象に含まれ、住宅取得資金分の500万円については、持ち戻しをする必要はありません。
ここまでが自分の認識していたことなのですが、
旧措置法70条3の2という平成21年に廃止された特例によると、この時は1,000万円の上乗せが精算課税2,500万円に加えて可能でした。
そして贈与者に相続が発生した場合、上乗せの1,000万円は精算課税の2500万円と同様、相続税の計算の対象に含まれることになるというものでした。
なので贈与を行なった年によって、相続税の計算の仕方が変わるので注意が必要となります。
ただし、過去に提出した精算課税の計算明細書に先程紹介した特例の適用を受ける欄にチェックが入っていれば見分けることができるので、資料確認というのが改めて大事なことだなと思いました。
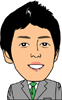
本日の発言者:池浦
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
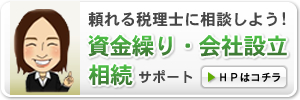
相続でお悩みの方は↓
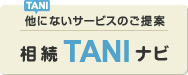
長くなってしまうので、2つの制度の基礎的な説明は割愛させて頂きます。
この2つの制度を併用して親から子へ住宅取得資金の贈与を行なった時に、精算課税分として、2500万円、住宅取得資金の非課税分として、500万円(一般住宅の場合です)の合計3,000万円について贈与税が非課税で贈与ができます。
そして将来親に相続が発生した場合、精算課税分の2500万円については、相続税の計算の対象に含まれ、住宅取得資金分の500万円については、持ち戻しをする必要はありません。
ここまでが自分の認識していたことなのですが、
旧措置法70条3の2という平成21年に廃止された特例によると、この時は1,000万円の上乗せが精算課税2,500万円に加えて可能でした。
そして贈与者に相続が発生した場合、上乗せの1,000万円は精算課税の2500万円と同様、相続税の計算の対象に含まれることになるというものでした。
なので贈与を行なった年によって、相続税の計算の仕方が変わるので注意が必要となります。
ただし、過去に提出した精算課税の計算明細書に先程紹介した特例の適用を受ける欄にチェックが入っていれば見分けることができるので、資料確認というのが改めて大事なことだなと思いました。
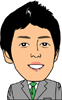
本日の発言者:池浦
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
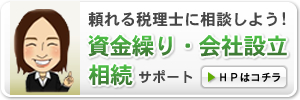
相続でお悩みの方は↓
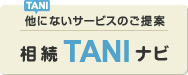
RECENT ENTRIES
最近の記事
CATEGORIES
カテゴリ
ARCHIVES
過去の記事
- 2026年02月(5)
- 2026年01月(6)
- 2025年12月(5)
- 2025年11月(4)
- 2025年10月(6)
- 2025年09月(7)
- 2025年08月(5)
- 2025年07月(8)
- 2025年06月(3)
- 2025年05月(5)
- 2025年04月(7)
- 2025年03月(5)
- 2025年02月(6)
- 2025年01月(4)
- 2024年12月(8)
- 2024年11月(8)
- 2024年10月(5)
- 2024年09月(4)
- 2024年08月(6)
- 2024年07月(6)
- 2024年06月(7)
- 2024年05月(6)
- 2024年04月(6)
- 2024年03月(7)
- 2024年02月(7)
- 2024年01月(7)
- 2023年12月(7)
- 2023年11月(5)
- 2023年10月(5)
- 2023年09月(7)
- 2023年08月(7)
- 2023年07月(10)
- 2023年06月(6)
- 2023年05月(5)
- 2023年04月(5)
- 2023年03月(5)
- 2023年02月(7)
- 2023年01月(6)
- 2022年12月(5)
- 2022年11月(7)
- 2022年10月(9)
- 2022年09月(8)
- 2022年08月(6)
- 2022年07月(8)
- 2022年06月(6)
- 2022年05月(8)
- 2022年04月(3)
- 2022年03月(8)
- 2022年02月(8)
- 2022年01月(5)
- 2021年12月(7)
- 2021年11月(7)
- 2021年10月(4)
- 2021年09月(7)
- 2021年08月(4)
- 2021年07月(7)
- 2021年06月(5)
- 2021年05月(7)
- 2021年04月(6)
- 2021年03月(9)
- 2021年02月(6)
- 2021年01月(5)
- 2020年12月(3)
- 2020年11月(8)
- 2020年10月(4)
- 2020年09月(8)
- 2020年08月(7)
- 2020年07月(8)
- 2020年06月(5)
- 2020年05月(5)
- 2020年04月(6)
- 2020年03月(9)
- 2020年02月(7)
- 2020年01月(4)
- 2019年12月(7)
- 2019年11月(7)
- 2019年10月(8)
- 2019年09月(6)
- 2019年08月(7)
- 2019年07月(10)
- 2019年06月(6)
- 2019年05月(7)
- 2019年04月(6)
- 2019年03月(4)
- 2019年02月(8)
- 2019年01月(7)
- 2018年12月(6)
- 2018年11月(9)
- 2018年10月(9)
- 2018年09月(5)
- 2018年08月(8)
- 2018年07月(9)
- 2018年06月(6)
- 2018年05月(9)
- 2018年04月(6)
- 2018年03月(6)
- 2018年02月(5)
- 2018年01月(5)
- 2017年12月(9)
- 2017年11月(9)
- 2017年10月(10)
- 2017年09月(3)
- 2017年08月(7)
- 2017年07月(5)
- 2017年06月(4)
- 2017年05月(8)
- 2017年04月(6)
- 2017年03月(4)
- 2017年02月(7)
- 2017年01月(3)
- 2016年12月(4)
- 2016年11月(5)
- 2016年10月(6)
- 2016年09月(5)
- 2016年08月(6)
- 2016年07月(6)
- 2016年06月(6)
- 2016年05月(7)
- 2016年04月(5)
- 2016年03月(6)
- 2016年02月(6)
- 2016年01月(5)
- 2015年12月(4)
- 2015年11月(6)
- 2015年10月(10)
- 2015年09月(3)
- 2015年08月(4)
- 2015年07月(9)
- 2015年06月(7)
- 2015年05月(5)
- 2015年04月(6)
- 2015年03月(9)
- 2015年02月(7)
- 2015年01月(5)
- 2014年12月(7)
- 2014年11月(7)
- 2014年10月(5)
- 2014年09月(9)
- 2014年08月(5)
- 2014年07月(9)
- 2014年06月(8)
- 2014年05月(5)
- 2014年04月(7)
- 2014年03月(7)
- 2014年02月(7)
- 2014年01月(6)
- 2013年12月(6)
- 2013年11月(7)
- 2013年10月(5)
- 2013年09月(5)
- 2013年08月(9)
- 2013年07月(5)
- 2013年06月(7)
- 2013年05月(8)
- 2013年04月(6)
- 2013年03月(7)
- 2013年02月(7)
- 2013年01月(5)
- 2012年12月(5)
- 2012年11月(9)
- 2012年10月(7)
- 2012年09月(4)
- 2012年08月(7)
- 2012年07月(4)
- 2012年06月(8)
- 2012年05月(6)
- 2012年04月(8)
- 2012年03月(6)
- 2012年02月(8)
- 2012年01月(4)
- 2011年12月(8)
- 2011年11月(6)
- 2011年10月(3)
- 2011年09月(12)
- 2011年08月(4)
- 2011年07月(8)
- 2011年06月(7)
- 2011年05月(6)
- 2011年04月(4)
- 2011年03月(7)
- 2011年02月(7)
- 2011年01月(8)
- 2010年12月(5)
- 2010年11月(10)
- 2010年10月(6)
- 2010年09月(7)
- 2010年08月(8)
- 2010年07月(8)
- 2010年06月(9)
- 2010年05月(10)
- 2010年04月(5)
- 2010年03月(9)
- 2010年02月(4)
- 2010年01月(4)
- 2009年12月(6)
- 2009年11月(7)
- 2009年10月(7)
